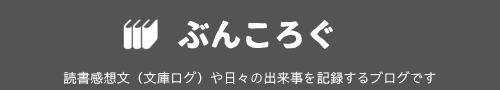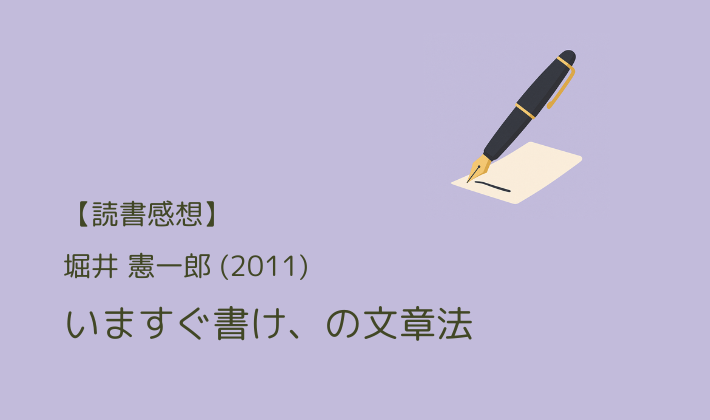| 書籍名 | いますぐ書け、の文章法 |
| 著者名 | 堀井 憲一郎 |
| 出版年 | 2011年 |
| 出版社 | 筑摩書房 |
書籍について
書籍の概要
人に読んでもらえる文章を書くにはどうしたらいいか、を説いている本です。
美しい表現とか、論理的な構成とか、そういう類の説明はありません。
文章はサービスであるという前提のもとに、文章を書く人が持つべきマインドセットから、具体的な書き方のテクニックまで、人に文章を読んでもらうために何をするべきか、ということを堀井先生が教えてくれる本です。
著者の紹介
コラムニストの方です。作家さんではないので、書籍のような文章ではありませんが、独特のユーモアがあって私はとても好きになりました。
この書籍を手に取った理由
2020年頃からぼんやりとブログをやってみたい、と思い始めていました。
でも、当時は何から始めればいいのかわからず、「ブログの始め方」をWebで調べていた時に、とあるサイトで本書が紹介されていたことがキッカケです。
そのサイトでは、ブログを始める人が読むべき本として2冊の本が紹介されていました。
1冊が本書で、もう1冊が「20歳の自分に受けさせたい文章講義」です。
もともと文章を書くのは好きだったので、とりあえず2冊とも購入することにしました。
この書籍を購入してから、実際にブログを始めるまでに5年かかりましたが、私にとってこの2冊はブログの原点のような書籍です。
こんな人におすすめ
文章を書きたいのに筆が進まないという人におすすめです。
本書のタイトルの通りに「今すぐ書け」と突き動かしてくれます。
実際に、私はこの書籍を読んで「文章を書いてみたい」という気持ちが湧いてきました。
ブログだけでなく、仕事のメールや資料作成で文章が書けない、という人にもおすすめします。
書籍からの学び
本書は9つの章で構成されています。それぞれの章に文章を書くためのヒントがあって、9つの異なった学びを得ることができます。
1章|プロとアマチュアの決定的な差
プロとアマチュアの決定的な差は、読み手のことを考えて書いているか否かにある。
プロは文章をサービスとして捉えている。自分の書きたいことを書いているのはアマチュア。
自分の主張をいったん曲げてでも読み手に楽しんでもらう、それくらいのサービス精神が必要。
文章はサービスなのだから、読みやすさも大事。
読みやすさとは、漢字を減らして、改行を増やすこと。
難しい漢字や不必要な漢字は、文章を読みづらくする。読者は漢字を学びたい訳ではない。
びっしりと文字が詰まった文章は、読み手を圧倒して読む気を失わせる。適度な改行が必要。
また、読者を特定した方が面白い。全人類に向けて書かれた文章はつまらない。
不特定多数に向けた文章だとしても、自らを「不特定多数」と思って読む人はいない。
誰が客なのか。文章がサービスである以上、誰に提供するのかを意識するべき。
2章|文章は人を変えるために書け
文章はサービス。
読み手が読む前と読む後で変わっていなければ、サービスの意味がない。
変わるとは、つまり、新しいことを知ること。
読み手が知らなかったことを知れる文章がおもしろい。逆に、自己表現だけの文章はつまらない。
人を変える文章を書くにはどうするのか。
人を変える、ということを意識して生きる。そうすると、ネタが自然に集まってくる。
テーマは小さくて構わない。たとえば「おいしい唐揚げの作り方」でも、人は変えられる。
3章|客観的に書かれた文章は使えない
文章は個人が発する私的なもの。公の視点で書かれた文章では、人は動かない。
書き手の独断と偏見で書くのが文章である。そうでない文章は読むに堪えない。
だから「独断と偏見ですが」と断りを入れない。読み手は、独断と偏見であることを百も承知。
また、文章には熱がないと面白くない。書き手に熱がなければ面白い文章にならない。
ただし、熱があれば良い訳でもない。そこには冷静さや理性が必要で、要はバランスが大事。
4章|直観のみが文章をおもしろくする
仮説を立ててから調査をする。
調査をすれば何かがわかる、ということはあり得ない。
では、どうやって仮説をたてるのか。
面白い企画は、とつぜん結論だけが思い浮かぶ、つまり直観である。
まず結論から。結論をひらめくことから始める。
5章|文章は言い切らないといけない
文章は強く書くことを意識する。
書く限りは、根拠を示して断定する。断定できないなら、書かずに調べ直す。
だから、文末に「思う」は使わない。
強く書くためには結論から書いて、その後に経緯を書く。
それが読み手にわかりやすいサービス。
結論を先に書くにはどうすればいいか。タイトルに結論を入れればよい。
6章|文章で自己表現はできない
文章を書く時に新たな語彙は必要ない。難しい言葉や美しい文章は必要ない。
文章を書く時に大事なのは削る作業。いかに文章をスリムにするか。
そもそも、文章は書き手のものではなく、読み手のものである。
7章|事前に考えたことしか書かれてない文章は失敗である
文章を書き始めると、新しいアイディアが浮かんで文章が思わぬ方向に行く。
そういう文章が良い文章になる。
文章が自走(ときに暴走)するのが、文章を書く醍醐味。
自分でも思わぬ展開になるのが面白い。
ただし、暴走した文章をまとめるのは難しい。だから、たくさん書いてトレーニングが必要。
8章|文章を書くのは頭ではなく肉体の作業だ
文章を自走させるために、読者をリアルに設定する。そうやって、書くことを繰り返す。
あとで書こう、ではなく、今すぐ書く。
そして、個性は身体に宿る。頭で考えるより、勢いよく書いた文章に個性が宿る。
個性が宿った文章の方が面白い。そのために、とにかく書く。
9章|踊りながら書け
締切が近くても楽観的に。
文章は頭で考えても進まない。動きながら考える。忙しい中でも書き続ける。
頭で考える前に、身体で確実にできることから始める。
アマチュアが腰を据えて書こうとしても進まないし、退屈なものになる。
身体から絞り出された勢いのある文章が面白い。
まとめ
本書を読む前に「綺麗な文章を書きたい」と思っていた自分がが恥ずかしくなりました。
文章を書くのは、人に読んでもらうため。
いくら綺麗な文章でも人に読んでもらえなければ意味がない、という当たり前のことに気付かされました。
そして、人に読んでもらうための学びとして自分に刺さったのは、テクニックやコンテンツよりもマインドに関するヒントでした。
文章をサービスとして捉えているか(1章)
人を変えるために書いているか(2章)
文章に熱を入れているか(3章)
文章を強く書くことを意識しているか(5章)
これらは、文章を書くにあたっての心の持ち方を問うてくれています。
気をつければすぐに変えられることなので、実践のハードルは高くありません。
すぐに試すことができるので、「よし、書いてみよう」という気になれます。
まさに、いますぐ書きたくなる、文章法です。